私が味音痴から脱却した理由とダージリン・アッサム飲み比べを始めたきっかけ
正直に告白すると、私は長年「味音痴」だと自分で思い込んでいました。紅茶を飲み始めて5年ほど経っても、ダージリンもアッサムも「なんとなく紅茶の味」としか感じられず、違いを聞かれても「うーん、どちらも美味しいですね」と曖昧に答えるしかありませんでした。
特に職場の先輩との会話で恥ずかしい思いをしたことがあります。「隆志くんは紅茶好きなんでしょう?このダージリンの香りってどう思う?」と聞かれた時、正直に言えば何も特別な香りを感じ取れませんでした。「いい香りですね」と当たり障りのない返答をしましたが、その後先輩が「この茶葉特有のマスカテルフレーバー※が素晴らしいよね」と語る姿を見て、自分の味覚や嗅覚に対する劣等感を抱くようになりました。
※マスカテルフレーバー:ダージリンの高級茶葉に特有の、マスカットのような甘い香りのこと
「味音痴」という思い込みから抜け出したきっかけ
転機となったのは、昨年の夏のことです。いつものように紅茶専門店で茶葉を購入していた時、店主の方から「飲み比べをしてみませんか?」と提案されました。その時に出していただいたのが、同じダージリンでも春摘み(ファーストフラッシュ)と夏摘み(セカンドフラッシュ)の2種類でした。
最初は「どうせ違いなんて分からないだろう」と半ば諦めていましたが、店主の方が「味音痴なんて存在しません。ただ、比較する機会と意識が足りないだけです」とおっしゃったのです。その言葉が私の心に深く響きました。
実際に飲み比べをしてみると、確かに何かが違うような気がしました。一方はより爽やかで、もう一方はより深みがあるような…。でも、それを言葉で表現することはできませんでした。
3ヶ月間の飲み比べチャレンジを決意した理由
その日から、私は「味覚は鍛えられる」という仮説を立てました。IT業界で働く私にとって、データ分析や継続的な改善は日常的な業務です。同じアプローチを紅茶の味覚開発にも応用できるのではないかと考えたのです。
そこで設定したのが以下の目標でした:
- 期間:3ヶ月間(90日間)
- 対象:ダージリンとアッサムの2種類に絞る
- 頻度:毎日必ず両方を飲み比べる
- 記録:感じた違いを必ず文字に残す
なぜダージリンとアッサムを選んだかというと、この2つは紅茶の基本中の基本でありながら、特徴が対照的だからです。ダージリンは「紅茶のシャンパン」と呼ばれる繊細な香りが特徴で、アッサムは濃厚でコクのある味わいが特徴です。この違いが分からないようでは、他の茶葉の違いなど到底理解できないと考えました。
また、忙しい社会人生活の中でも継続できるよう、朝の15分間を「紅茶の時間」として確保することにしました。朝の集中力が高い時間帯に、前日の疲れがリセットされた状態で味わうことで、より敏感に違いを感じ取れるのではないかという仮説もありました。
この挑戦を始めた当初は、正直なところ半信半疑でした。しかし、「データを取り続ければ必ず何かが見えてくる」という仕事での経験を信じて、まずは1週間続けてみることから始めました。
最初は本当に同じ味だった!紅茶の違いが分からなかった3つの理由
正直に告白すると、紅茶を飲み始めた当初の私は、どの紅茶も同じような味にしか感じられませんでした。友人から「ダージリンは繊細で上品な香り」「アッサムは濃厚でコク深い」と説明されても、私にはただの「苦い茶色い飲み物」でしかなかったのです。
今思い返すと、紅茶の違いが分からなかった理由は明確に3つありました。同じような経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
理由1:味覚の準備ができていなかった
最大の問題は、紅茶の微細な違いを感じ取る味覚が育っていなかったことです。当時の私は、普段からコーヒーやジュースなど、強い味の飲み物ばかりを摂取していました。
特に、仕事中は缶コーヒーを1日3〜4本飲む習慣があり、舌が強い刺激に慣れてしまっていたのです。紅茶の繊細な香りや味わいの違いを感じ取るには、まず味覚をリセットする必要がありました。
実際に、紅茶を飲み始めてから最初の2週間は、どのダージリンを飲んでも「なんとなく渋い」程度の感想しか持てませんでした。味音痴だった私の舌では、茶葉の個性を捉えることができなかったのです。
理由2:淹れ方が統一されていなかった
二つ目の理由は、淹れ方がバラバラで比較の条件が整っていなかったことです。
当時の私は、紅茶の淹れ方について深く考えたことがありませんでした。お湯の温度は「なんとなく熱め」、蒸らし時間は「適当に3分くらい」、茶葉の量も「ティースプーン1杯程度」と、すべてが感覚頼りでした。
| 項目 | 当時の私 | 正しい方法 |
|---|---|---|
| お湯の温度 | 沸騰したお湯をそのまま | 95-100℃(茶葉により調整) |
| 蒸らし時間 | 感覚で2-5分 | 茶葉に応じて3-5分 |
| 茶葉の量 | 目分量 | カップ1杯につき2-3g |
この不安定な淹れ方では、同じ茶葉でも毎回違う味になってしまい、茶葉本来の特徴を把握することは不可能でした。ダージリンの繊細なマスカテルフレーバー※も、適切に抽出されなければ感じ取ることができません。
※マスカテルフレーバー:ダージリンティー特有の、マスカットのような甘い香り
理由3:集中して味わう習慣がなかった
三つ目の理由は、紅茶を飲む際の意識の問題でした。
仕事をしながら、スマートフォンを見ながら、テレビを見ながら…といった「ながら飲み」が当たり前になっていた私は、紅茶の味に集中することがありませんでした。
忙しい社会人生活の中で、飲み物は単なる「のどの渇きを潤すもの」でしかなく、味わいを楽しむという発想自体が欠けていたのです。
特に、紅茶の香りについては全く意識していませんでした。カップを鼻に近づけて香りを楽しむなんて、当時の私には「面倒くさい」としか思えませんでした。しかし、紅茶の個性の多くは香りで決まります。この重要な要素を無視していては、違いが分からないのも当然でした。
この3つの理由により、どんなに高品質なダージリンを飲んでも、私には「普通の紅茶」としか感じられませんでした。しかし、これらの問題点を一つずつ解決していくことで、確実に味覚は変化していったのです。
ヶ月間の毎日飲み比べ実践記録:準備したものと具体的な手順
実践に必要な準備:厳選した茶葉と道具一式
まず、3ヶ月間の飲み比べ実践を成功させるために、私が準備したものをご紹介します。最初の準備が実践の成否を左右すると実感したので、特に重要なポイントをお伝えします。
茶葉については、ダージリンとアッサムそれぞれ2種類ずつ、計4種類を用意しました。ダージリンは春摘み(ファーストフラッシュ)と夏摘み(セカンドフラッシュ)、アッサムは異なる茶園のものを選択。これは単純に2種類だけでは違いが分からなかった私の失敗経験から学んだ選択です。
道具面では、ティーポット2個、ティーカップ4個、デジタルタイマー、温度計、そして記録用ノートを準備しました。特に温度計は重要で、お湯の温度によって茶葉の特徴が大きく変わることを後に実感することになります。
毎日の実践手順:忙しい社会人でも続けられる方法
実際の飲み比べは、平日の朝と夜、週末の午後に実施しました。限られた時間で効率的に進めるため、以下の手順を確立しました。
| 時間帯 | 実施内容 | 所要時間 | 記録項目 |
|---|---|---|---|
| 朝(7:00-7:20) | ダージリン2種飲み比べ | 20分 | 香り、渋み、後味 |
| 夜(21:00-21:20) | アッサム2種飲み比べ | 20分 | コク、色味、ミルクとの相性 |
| 週末午後 | 4種類総合比較 | 40分 | 全体的な印象、変化の記録 |
蒸らし時間は3分で統一し、お湯の温度はダージリンが85-90度、アッサムが95-100度に設定しました。この温度管理により、それぞれの茶葉本来の特徴を最大限引き出すことができます。
記録システム:味覚の変化を可視化する工夫
単に飲み比べるだけでは効果が薄いことを1週間目で実感し、独自の記録システムを構築しました。5段階評価と具体的な言葉での表現を組み合わせた方法です。
香りについては「青草のような」「花のような」「土っぽい」といった具体的な表現で記録。渋みは1(全く感じない)から5(非常に強い)の数値で評価しました。この数値化により、自分の味覚の変化を客観的に把握できるようになります。
特に効果的だったのは、「今日の発見」欄を設けたことです。「ダージリンの香りに柑橘系の要素を感じた」「アッサムをミルクティーにすると甘みが増す」など、小さな気づきを記録することで、味覚の成長を実感できました。
1ヶ月目は正直、ほとんど違いが分からず「本当に効果があるのか」と不安になりましたが、記録を見返すと微細な変化が蓄積されていることが分かります。2ヶ月目に入ると、明らかに香りの違いを感じられるようになり、3ヶ月目には「この香りはダージリンのセカンドフラッシュ特有のマスカテルフレーバー※だ」と確信を持って判別できるレベルに到達しました。
※マスカテルフレーバー:ダージリンの夏摘み茶葉に特有の、マスカットのような上品で甘い香り
この実践記録システムは、忙しい社会人の方でも無理なく続けられる設計になっており、紅茶の知識を体系的に身につけたい方には特におすすめの方法です。
ダージリンとアッサムの基本的な違いを理解するまでの道のり
最初の2週間は、正直なところ「これって本当に違いがあるの?」と疑問に思うほど、どちらも「ただの紅茶」にしか感じられませんでした。IT業界で働く私にとって、味覚の違いを理解するというのは、プログラミングのデバッグとは全く異なる種類の学習でした。
産地の違いから理解を始める
まず基本情報として、ダージリンはインドの西ベンガル州にある高地で栽培され、アッサムはインド北東部の平地で栽培されています。この地理的な違いが、茶葉の特徴に大きく影響することを理解するのが第一歩でした。
私は毎日の飲み比べ記録をExcelシートに記録していましたが、最初の1週間はコメント欄に「よくわからない」「どちらも同じような味」という記録ばかりでした。しかし、2週間目に入った頃から、少しずつ違いが見えてきました。
| 特徴 | ダージリン | アッサム |
|---|---|---|
| 茶葉の色 | 明るい茶色 | 濃い茶色 |
| 水色(すいしょく) | 薄いオレンジ色 | 濃い赤褐色 |
| 香りの印象 | フルーティーで爽やか | 麦芽のような甘い香り |
| 渋みの強さ | 上品で軽やか | しっかりとした渋み |
味覚の違いを実感した転機
3週間目に入った頃、朝の忙しい時間帯にダージリンを飲んだ時、「あれ、今日は軽やかな感じがする」と初めて明確に感じました。その日の夕方にアッサムを飲んだ時、「こちらは重厚感がある」と対比で理解できたのです。
この時の発見をきっかけに、私は対比による理解を意識的に行うようになりました。同じ日の朝と夕方で飲み比べることで、記憶が新しいうちに違いを比較できるようになったのです。
専門用語の理解が深めた認識
1ヶ月目の終わり頃、ダージリンの特徴である「マスカテルフレーバー」(マスカット様の香り)について調べました。この香りを意識して飲むようになると、確かにダージリンからは果実のような甘い香りがすることに気づきました。
一方、アッサムの「モルティーフレーバー」(麦芽様の香り)も理解できるようになりました。これは焼いた麦のような香ばしさで、朝食のパンやシリアルと合わせると特に感じやすいことが分かりました。
実際の変化の記録:
– 1週目:「違いが分からない」が90%
– 2週目:「なんとなく違うかも」が30%
– 3週目:「明確に違いを感じる」が60%
– 4週目:「好みの違いまで分かる」が80%
この段階的な理解の深まりは、毎日継続することでしか得られない貴重な体験でした。特に忙しい社会人の方には、朝の5分間だけでも意識的に味わう時間を作ることをお勧めします。
味覚を鍛えるための記録方法:私が実際に使った評価シートを公開
味覚を鍛えるための記録方法について、私が実際に使った評価シートを公開します。最初は「何を記録すればいいか分からない」状態でしたが、試行錯誤を重ねて現在の形に落ち着きました。
基本評価シートの項目設定
私が使用している評価シートは、A4用紙1枚に収まるシンプルな構成です。項目は以下の通りです:
| 項目名 | 評価方法 | 記録のポイント |
|---|---|---|
| 茶葉の種類 | 正確な商品名を記載 | ブランド名、グレード、産地まで詳細に |
| 抽出条件 | 温度・時間・茶葉量 | 毎回同じ条件で統一 |
| 香り | 5段階評価+コメント | 最初の印象と時間経過後の変化 |
| 渋み | 5段階評価 | 舌のどの部分で感じるかも記録 |
| コク | 5段階評価 | のどごしの重さや余韻の長さ |
| 総合評価 | 10点満点 | 個人的な好みも含めた総合判断 |
特にダージリンの評価では、マスカテルフレーバーの強さを別項目で記録しています。これは他の茶葉にはない独特の特徴なので、専用の評価軸を設けることで違いが明確になりました。
記録を続けるための工夫
最初の1ヶ月は毎日記録するのが大変でした。そこで以下の工夫を取り入れました:
スマホアプリとの併用
紙の記録だけでは外出先で確認できないため、スマホのメモアプリにも同じ内容を記録。これにより、お店で茶葉を購入する際に過去の評価を参考にできるようになりました。
写真による記録
茶葉の色、抽出した紅茶の色も重要な判断材料です。毎回同じ角度、同じ明るさで撮影し、評価シートと一緒に保存しています。
比較飲みの記録方法
週末は必ず2種類の茶葉を同時に飲み比べ、違いを明確に記録します。例えば「アッサムCTCとダージリンセカンドフラッシュの比較」といった具合に、対比させることで特徴がより鮮明になります。
データ分析による成長の可視化
2ヶ月目からは、記録したデータを週単位で振り返る習慣を始めました。
味覚の変化を数値で追跡
同じ茶葉に対する評価の変化をグラフ化することで、自分の味覚の成長を客観視できます。最初は「渋み2」だったダージリンが、1ヶ月後には「渋み4」と感じるようになり、より繊細な違いを感じ取れるようになったことが数値で確認できました。
好みの傾向分析
高評価をつけた茶葉の共通点を分析し、自分の好みのパターンを発見。これにより、新しい茶葉を選ぶ際の指針ができました。
記録を続けることで、単なる「美味しい・美味しくない」から「なぜ美味しいのか」「どこが違うのか」を言語化できるようになります。忙しい平日でも5分程度で記録できるよう、項目を厳選したのがポイントです。
この評価シートを使い始めてから、同僚との紅茶談義でも具体的な表現ができるようになり、コミュニケーションツールとしても役立っています。
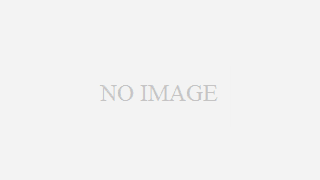
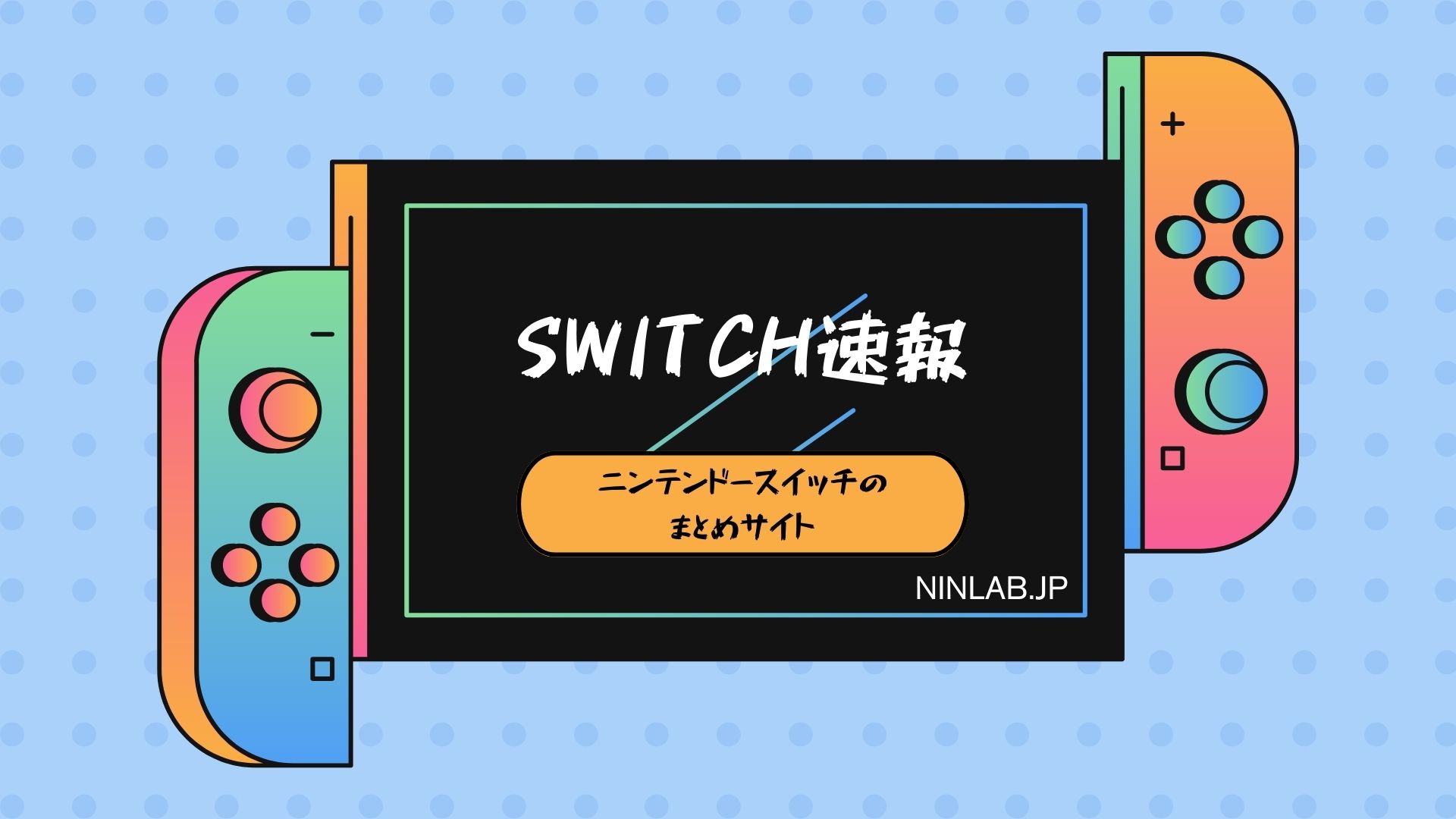
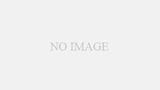
コメント